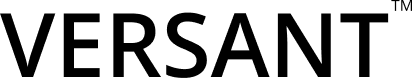日本酸素ホールディングスは2020年、米国・欧州・豪州・アジアへの海外売上高比率の高まりとともに、さらなる成長のために日本事業を中心とした経営から、グローバル運営体制を構築すべく、純粋持株会社が各事業会社を管理するいわゆるホールディングス体制となった。
ホールディングス体制への移行に伴い、グローバルカンパニーとして海外の各事業会社と共通言語となり得る英語によるコミュニケーションとグローバルネットワーキングの構築を図ることが必須となり、英語学習の機会を促進する。 社員の英語能力のレベルアップ確認や海外駐在員の学習意欲をサポートするために「Versant」を活用する。
グローバルで活躍する社員のレベルアップを支える
活用内容
世界各地で働く社員たちのエンゲージメントを推進する施策として「人財交流プログラムの推進」「ダイバーシティ&インクルージョン」を掲げ、2021年より「Versant」を取り入れた語学力向上プログラムを導入。毎年、ホールディングスから約70人と海外駐在員約60人が「Versant」を受験する。
英会話研修およびVersant導入の目的
- 実践的な英語力を備える人材の育成
- グローバルネットワーキングの構築
日本酸素ホールディングスにおける事業課題
- グループ全体でシナジー創出のためのネットワーキング
- 消費地立地のビジネスを生かした、各国のベストプラクティスの共有
※本記事は、人事部 人事課長 柴田氏と経営企画室 川野氏への取材に基づき構成しています。
世界でシナジーを生み出す
ネットワーク構築へ
グローバルな連携が各部署で急速に進むなか、
海外派遣要員だけでなくグローバルコミュニケーション能力に
長けた人材を一人でも多く育成する。(柴田氏)
グローバルな連携が各部署で急速に
進むなか、海外派遣要員だけでなく
グローバルコミュニケーション能力
に長けた人材を一人でも多く育成
する。(柴田氏)
まず、「Versant」を活用いただく背景について教えてください。
柴田 2020年にホールディングス体制になり、グローバルカンパニーとしてふさわしい組織や制度の構築を進めるなか、世界各地で働く社員たちのエンゲージメント向上や親密なネットワークが大きなミッションとなりました。特にホールディングスではグローバルコミュニケーション能力が必要不可欠で、仕事に直結した英語研修プログラムをスタートさせました。コミュニケーション力を上げることを主眼とし、スピーキング力を測る目的で「Versant」の採用を決定しました。実践で使える英語力を測るには「Versant」が最適です。
当社の主力である産業ガスのビジネスは現地で完結する消費地立地型ビジネスで、これまで他国との交流や情報交換などは活発ではありませんでした。ホールディングス体制になり、各地域のベストプラクティスを共有することでグループ総合力を発揮し、さらなる成長を目指すことができます。具体的には、事業を取り巻くリスクと機会を様々な視点で議論し、各社の成功事例を共有する「オペレーショナル・エクセレンス」を始動しています。四半期ごとに各エリアで定例ミーティングを行い、年に1回は全世界のグループ企業代表がオンライン上に集い、成功事例をプレゼンテーションします。
こうした交流を活発にするには、海外派遣要員だけでなくグローバルコミュニケーション能力に長けた人材を一人でも多く育成することが重要です。

攻略法がないからこそ、
実践的な学習に真摯に取り組める
参考書のような攻略法がないからこそ、
実践的な学習にまっすぐ取り組めるのが魅力だと思います。
(川野氏)
参考書のような攻略法がないから
こそ、実践的な学習にまっすぐ
取り組めるのが魅力だと思います。
(川野氏)
「Versant」はグローバル人材育成にどのように貢献していますか。
柴田 「Versant」は年2回の受験を推奨しています。まずは現状の実力を正しく理解してもらい、オンライン英会話レッスンでサポートしながらスコア47点(GSE 43)を目指してもらいます。このスコアを1つの基準に据え、次のレベルへ進むか、同じレベルのレッスンを継続するかを判断してもらうようにしています。
川野 スコアは社内や部署の意識向上に大きく貢献しています。大幅に点数アップした人に話を聞くと、「好きな映画の主人公の英国なまりをシャドーイングしてみた」「毎日積極的に外国人と英語で話すよう心掛けている」といった様々な取り組みを共有したりもしています。参考書のような攻略法がないからこそ、実践的な学習にまっすぐ取り組めるのが魅力だと思います。
ホールディングスのほかに、事業会社の様々な部門ではどのようなシーンで英語のコミュニケーション力が求められるのでしょうか。
柴田 海外事業会社との業務上の連携がある部署では一定以上の語学力が求められます。例えば、国内外が連携するITインフラに関わるプロジェクトでは、メールやオンライン会議ベースでの英語コミュニケーションスキルが必要です。また、品質保安での連携では、日本の安全基準に関するベストプラクティスの紹介・推進のために、海外メンバーとのオンライン会議や現地でのミーティングなどがあります。そのほか、海外展示会に出展する機会には、準備段階で海外事業会社や海外イベント会社との折衝、展示会の期間中には来場者に英語で直接説明しなければなりません。英語で聞いて、理解して即時に反応する、「Versant」が測定する力が問われています。
英語でのコミュニケーション力向上を目指す従業員の中で、Versantスコアを指標の一つとしたレベル別の人事部主催英会話ワークショップを2コース設けて実施しています。
日々の英会話オンライン研修は「練習」で、英語を使った業務(英語会議や出張など)を「試合」とみなした場合、ワークショップは練習試合の役割を担います。
オンライン英会話学習の各人習得効果を測る方法の一つとして「Versant」を受験しており、そこで見つけた自身の弱点や課題を認識してもらうことが重要です。弱点や課題が明確になれば、そこにフォーカスしてオンライン英会話学習に役立てて欲しいと、人事部からも声掛けをしています。

世界に広がるグループの強みを
最大限に生かすために
多様性を強みにするには
グローバルコミュニケーションが不可欠、
そのベースとなるのが英語力です。(柴田氏)
多様性を強みにするには
グローバルコミュニケーションが
不可欠、そのベースとなるのが
英語力です。(柴田氏)
最後に、グローバル人材育成の展望についてお聞かせください。
柴田 先ほどご紹介した「オペレーショナル・エクセレンス」は世界に広がるグループの強みを最大限に生かすための施策の1つです。様々な成功例を発表し合うだけでなく、それを各企業や拠点が取り入れる、あるいはさらに発展させるアイデアを意見するなど、深い交流へと導くのはグローバルコミュニケーションであり、そのベースとなるのが英語力です。
当社は様々な企業がグループとなり、いまの形態になりました。さらにダイバーシティを進めることで国内でも外国人の割合が増え、異文化や様々な国や地域の商習慣などが浸透するはずです。それを次への成長の糧にするには、強固なグローバルネットワーキングの構築がカギを握ります。日本発のグローバルガスメジャーとして競争力のある運営体制を構築し、グループ総合力を生かしながらグローバルでの持続的成長を目指していきたいと思います。
(※掲載情報は取材当時のものです)